活動報告
オンライン意見交換会(2025年6月21日)
神経筋疾患患者登録サイトRemudyについて、当分科会会員で意見交換を行いました。
Remudyでは2009年からBMDの患者登録を開始していますが、BMDの国内推定患者が約1,500人である一方、患者登録数は458名(2025年4月30日時点)に留まっているという課題があります。
BMD分科会として、さらに登録者数を増やすための改善点や方策、Remudyの効果的な周知・普及方法について議論しました。
今後はBMD分科会としての意見を整理し、Remudyの関係者にお伝えする予定です。
第7回オンライン交流会(2024年10月26日)
第7回オンライン交流会をZOOMにて開催しました。当日は全国各地から15名以上のBMD当事者やそのご家族の方々にご参加いただき、約2時間にわたり交流させていただきました。
冒頭では、AOMC-JMC2024の参加報告や筋ジストロフィー医療研究会の開催案内をさせていただき、また、BMDのドラッグ・ロス(海外では使用が認められているが、日本では治験が行われず使用が認められていない治療薬がある状況のこと)の現状について参加者の皆さんに共有させていただきました。
後半では、車椅子やおすすめのPC周辺機器について情報交換しました。
第3回オンライン交流会(2023年1月28日)
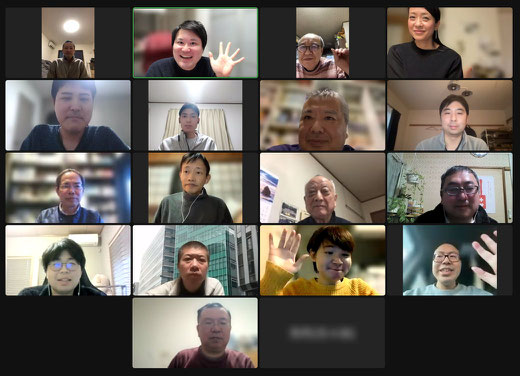
第3回オンライン交流会をZOOMにて開催しました。当日は全国各地から18名のBMD当事者やそのご家族の方々にご参加いただき、約2時間にわたり交流させていただきました。
常連の方から初めてのご参加の方までおりましたので、みなさんにリレー形式で自己紹介いただきながら、病気に関すること、制度のこと、日々の困りごと、生活での工夫・知恵について共有していきました。
第2回オンライン交流会(2022年8月28日)

第2回オンライン交流会をZOOMにて開催しました。当日は全国各地から15名のBMD当事者やそのご家族の方々にご参加いただきました。約2時間にわたり交流させていただき、今回もまだ2回目で初めてのご参加の方が多く、みなさんの自己紹介の時間がメインとなりました。
今後は、病気に関すること、制度のこと、日々の困りごと、生活での工夫・知恵などを共有する場にできればと考えています。
第8回日本筋学会学術集会筋学会(2022年8月5日~6日)
第8回日本筋学会学術集会に本分科会副会長の柴﨑が参加しました。
日本筋学会は、歴史ある日本の筋の基礎研究を発展させ、また様々な筋疾患を克服するために、学際的な組織として2015年に誕生しました。
一般口演では、宮崎大吾先生(信州大学・医学部附属病院・講師)が「重症度の異なる複数のベッカー型筋ジストロフィーモデルマウスを用いた重症化機序に関する研究」と題して、ベッカー型モデルマウスの病態について発表されました。
また、ポスター発表では、中村昭則先生(当分科会顧問、国立病院機構まつもと医療センター・臨床研究部長/脳神経内科部長)が「臨床開発を目指したベッカー型筋ジストロフィーの自然歴調査研究」の研究成果について発表されていました。
少しずつですが、BMDの研究も進んできています!
第1回オンライン交流会(2022年6月4日)
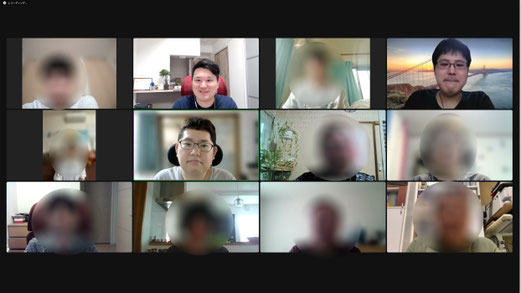
BMD分科会発足後、初のオンライン交流会をZOOMにて開催しました。当日は全国各地から15名のBMD当事者やそのご家族の方々にご参加いただきました。約2時間にわたり交流させていただき、初めてということで自己紹介の時間がメインとなりました。
